
ビュッフェ形式の学びへ#特別1_勉強するのは何のため?授業公開を終えて
みなさん、こんにちは。
関西創価中学校英語科の津田奈々世です。
2学期も半ばに入り、SoFELの学びも半年が経とうとしています。
今日は、私たち教員が見てきた生徒の変化を綴り、これからの学びを共に考えてみたいと思います。
生涯学習者を育てたい
一斉学習、探究型学習、自律型学習、アクティブラーニングなど、手法は授業者によってさまざま。すべてに共通して言えることは、そこに【学習者の目的感】がないと、どれも強制的で受け身な学びになってしまう、という点です。
興味深いデータがあります。(参考文献:石田勝紀著「同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか?」)
一斉授業のなかで、果たしてどれだけの生徒が主体的に学べているかという研究の結果です。
「学び」には主に3つのタイプがあるそうです。
①授業を受けていても学んでいない人
②授業だけが学びの人
③寝ているとき以外、日常すべてが学びの人
悲しい話ですが、実は①の割合が一番多いんだそうです。
このタイプは、イスには座って、黒板に書いてあることを書き写す「作業」を黙々と行い、たまに教員の雑談が始まると聞く耳スイッチが入りよく聞いて反応までする…
かくいう私も、こういう瞬間多かったな~と反省します。
子供たちにとって、学校生活の中の非常に多くの時間を占める授業を、このように過ごしていたのでは、もったいない話ですね。この割合は全体の69%にあたるそうです。40人学級で考えると約28人。
次に多いのが、②授業だけが学びの人(勉強の場だけが学びの人)です。このタイプの人は、授業中にしっかり学び、家庭学習もある程度習慣づいている人が多いそう。全体の24%といわれているので、40人学級だと約10人ですね。
最後に、③寝ているとき以外日常すべて学びの人です。
「いやいや、そんな人いるの?」と感じるかもしれませんが、東京大学には特にこういうタイプの人が多いそうです。全体の7%がこのタイプに分類されるそうで、40人学級だと約3人が、日常からすべてを感じ、学びとして吸収していってるのです。
いくら教員が「よい授業をせねば」と思って、知識を与え続けたとしても、学習者側の意識による影響がとても大きいのが現実です。
この3つのタイプが、そのままビジネスパーソンに置き換えられるとしたらどうでしょうか。大半の人が、与えられたこと以上はしない人材になってしまうという不安も感じます。

目の前にいる子供たちには、どうかAI時代を強く生き抜く学力(学ぶ力)をつけてほしいと願い、毎日試行錯誤しています。
勉強するのは何のため?
先日聖教新聞に記事が掲載されていた、哲学者・教育学者である苫野一徳氏は著書でこう述べています。
役に立つのかわからない、なんでやらされるのかわからない勉強を強制されるより、自分の関心にできるだけそって、みずから課題を設定しそれをクリアしていくという学びのスタイルを中心にしたほうが、「強制されている」という感じは、少なくとも今よりはずいぶんなくなるんじゃないかと思います。とすれば、じぶんなりの勉強する意味もまた、きっと今より見つけやすくなるはずです。
上記の苫野さんの言葉を読んで、「やっぱり子供たちに『勉強を強制する』のやめよう!」とすっきりしました。
だって、「アラビア語を1年でマスターして」と会社で強制されても、納得できる理由もなく私は頑張れないなと思うからです。
SoFELのように学習者主体の授業展開に対して、たいていの大人は「子供たちがサボるのではないか」という心配をしてしまうと思います。
ですが、何より子供たち自身が見守り応援してくれている保護者の方に心配はかけたくないと思う一面を持っています。
以下は私の考えです。
「勉強を任せて、子供がさぼったー。」
これは、これまで子供たちが勉強を任された経験がなく、またトレーニングもしてこなかったから。
子供たちが自律していない現状を作り出したのは、私たち大人の責任です。なぜなら、目標も決めないままに「これが大事」「あれが大事」と教え続け、自律する機会を奪ってきたから。
「なんのための勉強なのか?」
生徒一人ひとりが597通りの答えを見出し、自律できるようサポートするのが私たち教員の仕事です。
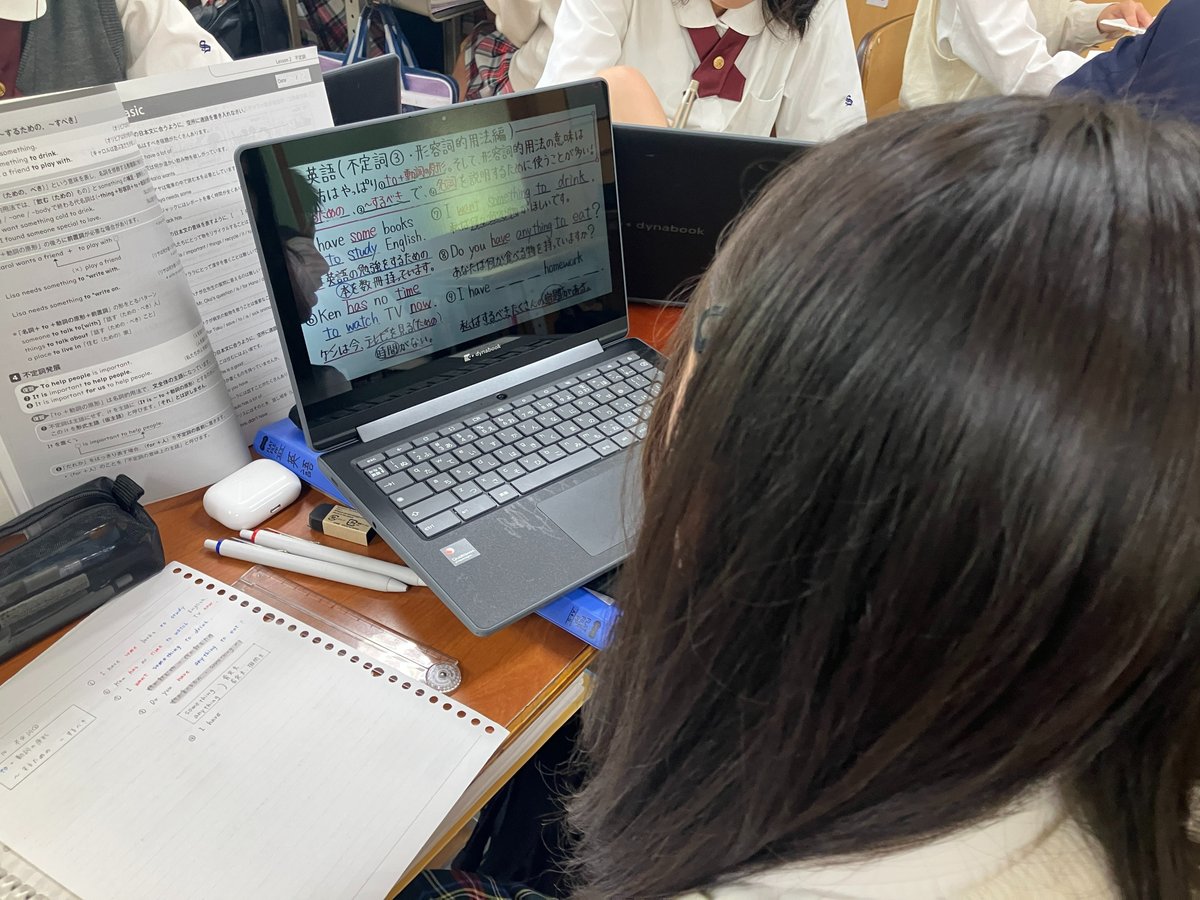
そのために私たち教員集団は、エンゲージメントの向上に努めています。易しい言葉で表現すると、「深いつながりをもった関係性や絆」を生徒一人ひとりと結べるよう、積極的に関わることです。
私自身、生徒への声かけ方法をまだまだ勉強中の身ですが、励ましは一方通行でなく対話的であらねばならないと、創立者の言葉からも学んでいます。
大切なのは、心を「軽く」してあげることだ。「強く」「明るく」して
あげることだ。(中略) 励ましの本義は、相手の幸福を願う心にある。
変化に強いこどもたち
熟考を重ね始まったSoFELですが、現在も、マイナーチェンジを行いながら、ベターな形を目指しています。
とくに「学び合い」クラスでは、本来取り組むべき単元の学習によりフォーカスして取り組めるよう、「単元内自由進度学習クラス」(2年生は課題設定クラス)と名称を変更し、スタンプシートをこれまでよりさらに活用し、問題集と教科書の問題に取り組むようにしました。子供たちが自律に向かうには、段階を踏むことも大事だという観点からです。
ある生徒がこんな励ましを送ってくれました。
「単元内自由進度クラスってなったから、今まで以上に、テストの勉強はこの日、検定の勉強はこの日って自分で決めて集中できます、ありがとうございます。」
不確実(VUCA)な時代に到達した今、環境適応力の必要性を生徒に教えてもらう場面が本当に多いです。ともに学ぶ教員集団も、環境にしなやかに対応できる大人でありたいと感じています。
「水辺の馬」という故事を皆さんはご存じでしょうか。
これは、「馬を水辺に連れていけても、水を飲ませることはできない」という、本人にその気がないのに、周りの人が強制しても無駄であることを意味した中国のことわざです。
この言葉を、次のように読み取ることもできるかと思います。
「水辺にいれば、そのうち水を飲むようになる」
もちろん、そのうちできるようになるまでの過程では、大変な瞬間もあるでしょう。あきらめそうな時だってある。
しかし、目標へとファシリテートしてくれる人が近くにいたらどうでしょうか。「今、自分の立てた目標に近づいてる?」「あと15分どうやって過ごそう?」と常に自分に問いかけていたら?


存分にチャレンジしてよいと感じる安全基地(アタッチメント)と自己修正(セルフコントロール)を通して、自分の手で自分を作りあげる一人ひとりに、成長してほしいと強く思っています。
子どもの幸福とは、子どもにすべてが与えられることでも、すべてが自分の思い通りになることでもない。自らがやりたいと思うことを自覚し、それに取り組むことができる環境があり、おこるであろう困難を乗り越えながら、実際に試行錯誤を繰り返す中で人間的に成長することではないだろうか。
